現在のF1は、レース中2種類以上のコンパウンドの異なるタイヤの使用義務があるため、
各ドライバーはレース中少なくとも1回はタイヤ交換をすることになります。
アンダーカット、オーバーカットを呼ばれる戦略に大きく影響するタイヤ交換後のラップタイムについて解説しようと思います。
必ずしもラップタイムは向上しない
タイヤ交換義務を果たすためピットインする、ということもありえますが、
基本的にはタイヤのデグラデーションによるタイムロスを回避する目的で
各ドライバーはタイヤ交換を行います。
しかし、交換後のほうがラップタイムが遅くなるということが考えられます。
この要因として、タイヤの作動温度領域、ピットアウト後の位置関係等が挙げられます。
タイヤの作動温度領域
タイヤには作動温度領域と呼ばれる、グリップ力が最大となる温度が存在します。
タイヤ交換直後はタイヤが冷えており、走り続けることでタイヤは温まりますが、
その間ラップタイムは遅くなります。
タイヤが温まるのにかかる時間は状況により様々で、タイヤの種類、路面温度、コース特性などに影響されます。
タイヤの種類については、柔らかいコンパウンドの方が温まりやすく、
硬い方が温まりにくいです。
ちなみに、予選Q2を突破したドライバーは、
Q2での最速ラップタイムを記録したタイヤでレースをスタートするというF1のルール、
スタートの蹴り出しは柔らかいタイヤの方が良いこと等の影響から、
基本的に柔らかいタイヤでレースをスタートし、
硬いタイヤに交換するという戦略を選択する事が多いです。
ピットアウト後の位置関係
タイヤ交換には、コース毎のピットロードの長さ、ピットロード内の制限速度、作業時間等が影響し、
概ね20秒程度のタイムロスが発生します。
つまりピットアウト後は一時的に20秒後ろのマシンとコース上で争い、そのマシンに詰まってしまいます。
現在のF1マシンはコース上でのオーバーテイクが難しく、
タイヤ交換を終えていないかつ、性能的に劣るマシンであっても
すんなりとオーバーテイクすることは出来ません。
このため、ピットインのタイミングは20秒後ろのマシンの台数や、間隔も考慮する必要があります。
実際2019年シンガポールGPでは、トップを走るフェラーリのルクレールが
タイヤマネジメント重視のペースで走行したため、各マシンの間隔が広がらず、
上位陣の20秒後方にマシンが密集していたため、膠着状態が続くという展開が見られました。
これらのことから、ピットアウト後のラップタイムは必ずしも向上せず、
オーバーカットもF1において有効な戦略と言えます。
アンダーカット、オーバーカットについては以下で解説しています。
また、ピットインのタイミングを決める大きな要素となる
セーフティーカーについては、以下の記事で解説しておりますので、
そちらをご覧ください。
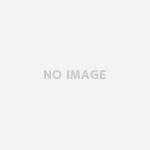
[…] F1 戦略 タイヤ交換後のラップタイム […]
[…] F1 タイヤ交換後のラップタイム […]
[…] F1 戦略 タイヤ交換後のラップタイム […]
[…] F1 戦略 タイヤ交換後のラップタイム […]
[…] F1 戦略 タイヤ交換後のラップタイム […]