F1では2022年シーズンからレギュレーションが大幅に刷新され、
マシンはグラウンドエフェクトカーへと変化すると言われています。
今回は、このグラウンドエフェクトカーについて、
グラウンドエフェクトのメリットとデメリットおよび
ダウンフォースの発生原理から、なぜマシン底部に空気を大量に送り込む必要があるのか
マシン底部と路面との距離を小さくかつ一定に保つ必要があるのかについて解説しようと思います。
グラウンドエフェクトとは
F1マシンは前方から流れてくる空気を利用し、
ダウンフォースを発生させ、タイヤのグリップ力を高めています。
このダウンフォースの発生方法は大きく分けて2つ存在します。
1つはマシンに取り付けられた様々なウイングにより空気の流れを制御し、
ダウンフォースを発生されるものです。
これは飛行機の翼で発生する上向きの力である揚力に対し、
逆向きの力を発生させると考えればわかりやすいと思います。
2つ目がマシンの底部に空気を送り込むことで、
マシン底部を低圧にすることでダウンフォースを得るというものです。
F1マシンは、これらのウイングとグラウンドエフェクトによる
ダウンフォースを同時に発生させていますが、
2022年からのレギュレーションではグラウンドエフェクトによる
ダウンフォースの比率が高まるということを意味しています。
ウイングとグラウンドエフェクト
ウイングによるダウンフォース発生原理はドラッグ(空気抵抗)も同時に発生させてしまうため、
コーナリングでの速度は向上するものの、ストレートでの速度は低下してしまいます。
一方、グラウンドエフェクトによるダウンフォース発生原理は、ドラッグを生じさせず
ストレートでの速度を犠牲にしにくいというメリットがあります。
また、ウイングに比べ、タービュランス(乱流、空気の乱れ)による影響が少ないため、
前方のマシンに近づきやすいこともメリットに挙げられます。
前方のマシンに近づきやすくし、バトルを増やす目的で、
2022年のレギュレーションでグラウンドエフェクトの比率が高めらました。
しかし、グラウンドエフェクトはマシンと路面との距離を一定に保つ必要があり、
縁石に乗り上げた時など、その距離が変化した際に一気にダウンフォースが抜けるため、
マシンの扱いが難しく、時には重大な事故を引き起こすという欠点もあります。
タイヤのグリップ力の向上になぜダウンフォースが必要かについては
以下の記事で解説しておりますので、そちらをご覧ください。
ダウンフォースの発生原理
グラウンドエフェクトはマシン底部に空気を多く送り込むことで、
マシン底部を低圧にすることで、マシン上部との圧力差によりダウンフォースを発生させます。
マシン底部に空気を多く送り込むと低圧にはならないようにも思えますが、
流体力学の2つの式を考えることでダウンフォースの発生原理が理解できます。
2つの式とは連続の式とベルヌーイの定理であり、これらについて簡単に解説します。
連続の式とは、流体力学における質量保存則のようなもので、
(断面積)×(流速)で表される流量が一定であるという式です。
この式から、マシン前方からマシン底部に流れる空気を考えると
空気がマシン底部に入ると、空気が流れることができる断面積が小さくなり、
マシン底部での空気の流速(流れの速度)が速くなります。
ベルヌーイの定理とは、流体力学におけるエネルギー保存則のようなもので、
運動エネルギーと圧力によるエネルギーの和で表されるエネルギーが一定であるという定理です。
この定理から、先程と同様にマシン前方からマシン底部に流れる空気を考えると、
マシン底部で流速が速くなれば、運動エネルギーが大きくなり、
その分、圧力によるエネルギー、つまりマシン底部での圧力が小さくなります。
これにより、マシン上部との圧力差が生まれ、ダウンフォースが発生します。
ダウンフォース発生原理のまとめ
長くなってしまってので、ダウンフォースの発生原理についてまとめます。
ダウンフォースの発生には、マシン底部で圧力を小さくする必要があり、
マシン底部で圧力を小さくするには、マシン底部での空気の流速を速くする事が重要です。
流速を速くするには、マシン底部へ流れる空気の流量を大きくすること、
およびマシン底部に空気が流れる流路を小さくすることが重要です。
このため、いかにマシン底部に空気を送り込めるか、
および、マシン底部と路面との距離を小さくかつ一定に保つことができるかが重要になります。
また、議論を簡単にするため触れませんでしたが、
マシン底部の空気を横方向に逃さないことも重要となります。
このため、マシンのフロア形状を工夫することで大きな渦構造を作り、
空気が逃げないように制御しています。
路面がウェットの場合には、水しぶきによりマシン付近の空気の流れが
よく見えるため、そこに注目するのも面白いと思います。
なお、ベルヌーイの定理は、同一流線上かつその流線上でエネルギーの損失および供給が
無視できる場合に成り立つため、正確な議論には注意が必要です。
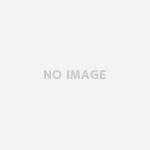
[…] F1 用語解説 グラウンドエフェクトカー […]