現代のF1はDRSなしには語れないと言っても過言ではありません。
実況解説でもことあるごとにDRSという単語が飛び交います。
F1におけるDRSとは何か。解説したいと思います。
DRSとは
DRSとは、Drag Reduction Systemの頭文字であり、日本語では空気抵抗低減装置です。
決勝レースの醍醐味であるオーバーテイクを促すために導入されたシステムです。
前を走るマシンとのタイム差が1秒を切った場合に、
リアウイングをたたむことで空気抵抗を減らすというシステムになります。
ただし、どこでもDRSが使えるというわけではありません。
各コースのストレート部分にDRSゾーン、その手前に検知ポイントが設定されており、
検知ポイントでのタイム差が1秒以内であればDRSゾーンでのDRSの使用が可能となります。
空力とDRS
現代のF1マシンは空力マシンであり、走行抵抗となる空気を、
ダウンフォースという形で利用しています。
なぜダウンフォースが重要なのかは以下の記事で解説しておりますので、
そちらをご覧ください。
このダウンフォースを得るために、マシンのあらゆる部分に
空気の流れを制御するパーツが取り付けられています。
これらのパーツにより、マシンに垂直方向下向きの力、つまりダウンフォースを与えています。
しかし、同時に空気抵抗、つまり走行抵抗も与えてしまいます。
コーナーではダウンフォースが欲しいが、ストレートでの走行抵抗は不要。
DRSによりこの両立が可能になったという訳です。
このDRSにより、オーバーテイクの回数は格段に増えたとされており、
レースの見どころが増えたとされています。
しかし、DRSによるオーバーテイクは、レースの本質とは異なるという意見や、
ストレートでのオーバーテイクは記憶に残らない等、否定的な意見も見られます。
2022年から新しく導入される規定では、
よりオーバーテイクのしやすいマシンを目標としており、
これによりオーバーテイクが増えれば、DRSは廃止されるという見方もあります。
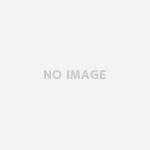
[…] F1 用語解説 DRS […]