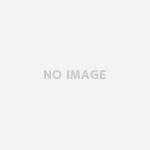フリー走行においてマシンの一部に黄緑色のペイントが
施されているのを見かけることがあります。
これはフロービズと呼ばれており、Flow Visualization Paintの略で、
マシン表面の空気の流れを可視化する塗料のことです。
今回は、フロービズの目的や、
なぜコース上でフロービズを用いるのかを解説しようと思います。
フロービズの目的
冒頭でも説明したとおり、フロービズの目的は
マシン表面の空気の流れを見ることです。
F1は、より少ない空気抵抗でより多くのダウンフォースを得るために
マシン各部にウイングを取り付け、改良を重ねています。
高度に科学技術が発展した今であれば、
最適な形状のウイングはすぐにでも開発できそうではありますが、
実は全くそんなことはないのが現実です。
これは空気の流れ、つまり流体力学の支配方程式である
ナビエ・ストークス方程式が複雑すぎることが主な要因です。
このため、ウイングにとどまらず、流体力学が関わる問題は
経験則で開発が進められることも多く、結果を検証する必要が出てきます。
しかし、空気の流れは目に見えるものではないため、
流れを可視化する必要があります。
その一つの手段として、フロービズを用いています。
フロービズをマシンに塗布し、実際に走行することで
マシン表面を流れる空気によりフロービズが流れ、
その様子を目で確認することができるようになります。
なぜコース上でフロービズを用いるのか
コース外でのマシンの開発には風洞を用います。
風洞とは、走行するマシンを模して、マシン前方から空気を当てる施設のことです。
コスト削減の観点から、風洞の使用には制限があり、
使用できるマシンの模型も、実際の60%以下のサイズという規定があります。
サイズが異なっていても同様の流れを作り出すことは理論的には可能ではあります
(最も基本的な考え方は流体力学の代表的は無次元数であるレイノルズ数を合わせること)が、
あらゆる方向から吹く風や、荷重変動や縁石によるマシンの動き等、
実際のコース上を走ってみないとわからない、再現できないことも多くあります。
このため、風洞とコース上での流れに違いがないかを確認するために、
コース上でもフロービズを用いています。
他にも、マシン周囲の流れを計測する機器として、
網目状にセンサーを取り付けたレーキと呼ばれるものや、
ピトー管などがあります。